日本航空輸送のスーパーエレクトラ絵はがきのロックヒードとロッキード
日 本 航 空 輸 送 株 式 会 社 旅 客 機
ロ ッ ク ヒ ー ド 1 4 WG - 3 型 1 1 人 |
ロ ッ キ ー ド F 14 W G 3 型 旅 客 機 (Lockheed
14WG3)
ライト・サイクロン875馬力2台・ 巡航速力325粁/時・旅客席10名・乗務員4名 |
1936(昭和11)年発行
日本航空輸送50年史 現有機集から
.JPG)
このように、ロッキードF-14スーパーエレクトラの機体説明に「ロックヒード」と「ロッキード」の二種類があり、例えば、ロッキード事件の被告人となった大久保利春氏が「ロックヒード」と言っていたのを思い出すというようなメールを頂きました。
また、LockheedはもともとLoughheadなので、「ロックヒード」ならぬ「ローグヒード」とした雑誌もあります。
なるほど、Lockheed Aircraft
Coの前身は、1916年にAllan LougheadとMalcolm
Loughheadの兄弟が設立したLoughhead Aircraft
Manufacturing Coです。
ちょっとややこしいですが、1926年に新会社とした際に綴りをLoughheadからLockheedにしたのは、音声発音にマッチさせるためだという説(
世界の航空機1952年7月号ロッキード40年史)があります。
(Lockheed Aircraft Coの傍系としてLoughheed Aircraftという会社もあるそうです
)
日本でロッキード機が一般化するのは、毎日新聞社が1932(昭和7)年に輸入したロッキード
アルテア通信機あたりからですから、既にLockheedが定着しております。それを「ロックヒード」と読むか「ロッキード」と読むかは、古い書籍では圧倒的に「ロックヒード」が多いですが、
絵はがきと同じように「ロッキード」としているものも、稀にはありました。
古い順にピックアップしてみます。
(A) 航空知識 1936(昭和11)年8月号 ロッキードと表示

(B) 航空事典 1938(昭和13)年発行 表題はロックヒード、図の説明はロッキードと混用
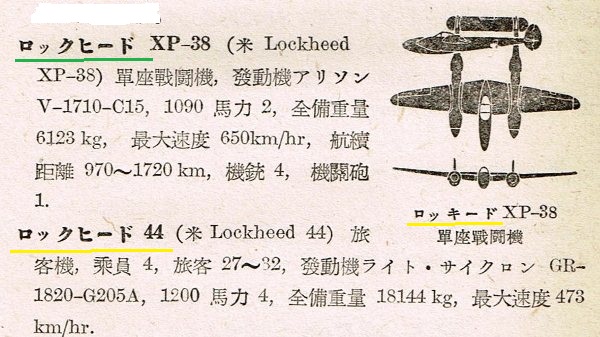
(D) 世界の航空機 1957(昭和32)年7月号ロッキード変遷史 解説野沢 正
ロッキード、ローグヒードを混用

こんな具合です。戦後においても(D)のように、同じページの同じ初飛行の機体
について社名が違うというようなことですから、(B)や(C)に見られる戦前はてんでんばらばらな感じです。
航空局企画課長までもが(部下の執筆でしょうが)平気で二つの呼称を使い、編集した朝日新聞社も気が付いていないというところに、名称への極めてずさんな対応を見るような気がします。

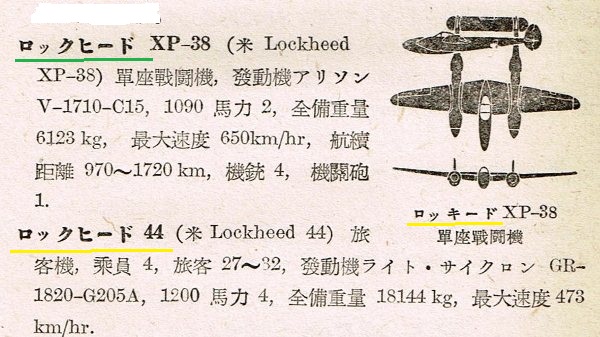
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)